法人口座が開設できない一番の理由は、銀行が「事業の実態や信用を確認できない」と判断するからです。
登記だけ済ませても、書類の不備や説明不足があれば審査は通りません。
では、どうすれば口座開設を断られずに済むのでしょうか。
ポイントはシンプルで、以下の3つを整えることです。
- 本人確認資料や登記簿の一致
- 事業の流れを示す契約書や請求書の提出
- 事務所や事業の実態を証明できる補足資料の提出
本記事では、公認会計士・税理士として数多くの企業の口座開設をサポートしてきた経験から、「断られる典型パターン」と「審査を通すための具体策」を解説します。
メガバンク・ネット銀行・信用金庫それぞれの特徴や、万一断られた場合の正しい対応方法まで網羅しています。
口座開設でつまずかないために、ぜひ押さえておくべきポイントを確認してください。
- 法人口座開設が断られる主な理由
- 銀行(メガバンク・ネット銀行・信金)ごとの審査の特徴
- 審査を通すために必要な書類と準備
- 口座開設を断られた後の正しい対応方法
1988年生まれ
公認会計士・税理士
2014年 EY新日本有限責任監査法人 入所
2021年 ニューラルグループ株式会社 入社
2022年 株式会社フォーカスチャネル取締役 就任
2024年 太田昌明公認会計士・税理士事務所 開業
2024年 ARMS会計株式会社 代表取締役社長
2025年 東京税理士会向島支部 幹事(役員)【税務支援対策部】
前職では上場会社の経理財務部長として勤務し、現在は経理・財務支援サービス会社を経営しています。
現職・前職では多数の法人口座管理経験があり、経理財務業務と会計業務のフロー構築は得意分野です。
銀行が法人口座開設を断られる主な理由|ネット銀行でも審査落ちする
法人口座の開設は「登記が済んでいれば当たり前に作れる」と思いがちですが、実際には多くの法人が審査で断られています。
特にネット銀行では利便性の高さと裏腹に、本人確認や事業実態の確認が一層厳しくなっており、「書類を揃えただけでは通らない」というケースも珍しくありません。
以下、公認会計士・税理士として実際に企業の財務・経理支援を行う中で見てきた「断られる典型理由」とその背景を整理します。
取引実態が不明確な法人は審査で落とされやすい
銀行が最も警戒するのは、「口座が事業に使われるのか、それとも不正目的に使われるのか」が判断できないケースです。
法人登記だけを済ませ、まだ売上や取引先の契約が一切ない場合は、どうしても疑われやすくなります。
実務上、銀行員は「この会社は実際に活動しているのか?」をシンプルに見ています。
私の関与先でも、請求書や取引先との契約書を提示することで、断られるリスクを回避できた例がありました。
逆に「名刺と登記簿だけ」で申請した会社は、法人口座開設を断られるケースもあります。
つまり「法人が動いていることを、客観的に示せる資料」を揃えておくことが最重要です。
本店所在地と事業実態の不一致は警戒される
登記簿上の本店所在地と、実際の事業活動の場所が異なる場合、銀行は慎重に確認を行います。
これは、登記住所と事業実態に乖離があると、事業の透明性を把握しづらくなるためです。
例えば、バーチャルオフィスやシェアオフィスを本店所在地として登記しているケース自体は珍しくありません。
スタートアップや小規模事業者にとって有効な選択肢となることも多いです。
ただし、その住所において実際に事業が行われているのか、あるいは単なる登録だけなのかを銀行は確認します。
実務で支援した事例では、シェアオフィスを本店所在地にしていても、契約書や郵便物の受け取り、実際の執務スペースの利用状況を明確に説明できたことで、問題なく口座開設が認められたケースもあります。
逆に、実態を示す資料が不足していた会社では、開設が難しかったこともありました。
つまり銀行にとって「住所=事業の実態」は重要な判断基準であり、シェアオフィスかどうかではなく、その場所で事業を運営していることを客観的に示せるかどうかが審査の分かれ目となります。
ネット銀行も本人確認と事業実態確認を厳格化している
「ネット銀行なら簡単に口座が作れる」と誤解されがちですが、ここ数年で状況は大きく変わりました。
オンライン完結の手軽さの裏で、犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認や事業確認のプロセスはむしろメガバンク以上にシビアになっています。
例えば、GMOあおぞらネット銀行や住信SBIネット銀行では、申請画面に入力した内容と登記簿・契約書・Webサイト情報を細かく照合します。
入力ミスや説明不足があるだけで、審査落ちになるケースを何度も見てきました。
ネット銀行はスピードとコストで優れる一方、「書類と情報の整合性」が厳格に求められます。
これは「手続きが楽=審査がゆるい」という意味ではない、という点に注意が必要です。
法人口座開設で断られやすい典型パターン|業種・住所・事業実態
銀行が法人口座開設の審査で注視するのは、「その法人に本当に事業の実態があるのか」「反社会的なリスクがないか」という点です。
特に、特定の業種や登記住所、事業の実績が乏しい法人は、他よりも厳しいチェックを受けやすい傾向にあります。
以下、実務でよく見られる「断られやすい典型パターン」を解説しつつ、どのように準備すればリスクを下げられるのか、実際の支援経験も交えて整理します。
投機性が高い・不透明な業種はリスクとみなされやすい
銀行は「安定した取引を継続できる業種」かどうかを重視します。
投機性が高いビジネス(例:仮想通貨取引仲介や海外投資関連)や、収益構造が分かりにくい業種は、マネーロンダリングや不正利用のリスクがあると判断されやすく、審査も厳しくなります。
ただし、これらの業種だから必ず断られるわけではありません。
実際に私が相談を受けた貿易企業では、中東の輸出入の関係で暗号資産を扱う事業であっても、取引先との契約内容や資金の流れを丁寧に説明した結果、無事に口座を開設できました。
何よりも大切なのは、ビジネスモデルを透明かつ理解しやすい形で示すことです。
バーチャルオフィスやレンタル住所は断られる可能性大
コスト面からバーチャルオフィスやレンタル住所を本店所在地にする法人は多くあります。
しかし、銀行から見ると「住所と事業の実態に乖離がある可能性がある」ため、必ず確認対象になります。
私のクライアントでも、シェアオフィスを利用していた法人が申請時に追加書類を求められましたが、実際の執務スペースの利用証明や郵便物の受け取り体制を提示することで、問題なく開設できた例があります。
要は「住所だけの法人」に見られないように、実態を示す補足資料を用意できるかどうかがポイントになります。
設立直後で事業実績がない法人は審査が厳しい
設立したばかりの法人は、まだ売上や取引実績がなく、銀行にとって事業の信頼性を測りにくいため、厳しく審査されることがあります。
これは「新設法人は一律で断られる」ということではなく、「事業実態を示す材料が少ないほど不利になる」という意味です。
私自身、設立1ヶ月の法人の開設支援を行った際には、事業計画書や想定取引先とのメールや見積書を補足資料として提示し、無事に審査を通過したことがあります。
銀行は未来の数字を期待するのではなく、「実際に事業を始める準備が整っているか」を見ています。
審査を通すために揃えるべき書類と準備事項
法人口座開設の審査で最も多い不備は「必要書類の不足」や「事業の実態を説明できないこと」です。
銀行は、法人の存在を確認する基本的な書類に加え、実際に事業が動いていることを裏づける資料を重視します。
私が公認会計士・税理士として支援してきた中でも、書類の揃え方ひとつで結果が大きく変わる場面を多く見てきました。
以下、最低限必要な書類から、審査を有利に進めるための準備まで整理します。
口座審査に必須の三要素|登記事項証明書・代表者情報・事業計画
銀行が口座審査で最初に見るのは「法人の存在」「代表者の信頼性」「事業の継続性」です。
これを示すのが登記事項証明書・代表者情報・事業計画の三点です。
- 登記事項証明書:法人の基本情報を裏づける必須書類で、発行から3ヶ月以内の最新のものが望まれます。
- 代表者情報:犯罪収益防止法の観点から重視され、本人確認書類に加えて追加資料を求められることもあります。
- 事業計画:設立直後の法人にとって実績の代わりとなる重要な材料です。取引予定先や契約書を添えて提示すれば、銀行の理解が得やすくなります。
この三要素は単なる形式ではなく、会社が「実在し、信頼でき、継続的に事業を行える」ことを示す証拠です。
不備があると口座開設は難しくなるため、準備は入念に行いましょう。
事業実態を示す契約書・請求書・ホームページの有無が重要
銀行は「この法人が実際に活動しているか」を非常に重視します。
そのため、取引先との契約書や請求書、また会社のホームページといった外部に見える情報は強力な裏づけとなります。
私が関与した事例でも、契約書1枚を提示できたことで銀行の姿勢が一気に前向きになったケースがありました。
反対に「名刺と定款だけ」では、どれほど熱意を説明しても審査は通りません。
つまり、事業を動かしている証拠を第三者に見せられるかどうかが決め手です。
オフィス写真や会社案内など補足資料で信頼度を高める
必須書類だけでは伝わりにくい「事業の実態」を補強するのが、オフィス写真や会社案内といった補足資料です。
銀行の担当者は、短時間で「この会社は実際に活動しているか」を判断しなければならないため、目で見て分かる資料があると大きな安心材料になります。
例えば、執務スペースや外観の写真、郵便物の受け取り状況を示す画像は、事業の稼働を直感的に伝えることができます。
また、会社案内やパンフレット、サービス紹介資料などは、第三者に対して「何をしている会社か」を一目で理解させる効果があります。
私が支援した設立直後の法人でも、事業計画や契約書に加えてオフィス写真と会社案内を提出したことで、「準備が整っている会社」と評価され、スムーズに口座開設が進んだ事例がありました。
つまり、補足資料は単なる「おまけ」ではなく、必須書類だけでは伝わらない事業の実態や誠実さを補強する武器です。
特に設立間もない会社や、取引実績がまだ少ない会社こそ、積極的に用意しておくべきだと言えるでしょう。
口座開設を断られたときの正しい対応|審査落ち後の再申し込みの銀行の選び方
口座開設を断られると「もうどこでもダメなのでは」と不安になりますが、実際には対応次第で再度の申請が通るケースは多くあります。
重要なのは、やみくもに複数行へ申請を繰り返すことではなく、落ちた理由を把握したうえで戦略的に行動することです。
以下、私が公認会計士・税理士として企業の資金管理や設立の相談支援に関わる中で得た経験をもとに、再申請時に押さえておくべき考え方を解説します。
同じ銀行への再申請は一定期間を空けるのが基本
一度断られた銀行にすぐ再申請しても、結果は変わりません。
銀行内部には審査履歴が残るため、短期間で再度申請すると「前回と同じ状況」と見なされ、再び断られる可能性が高くなります。
実務経験でも「3ヶ月以内の再申請はほぼ通らなかった」というケースを多く見てきました。
改善点があれば、数ヶ月程度の期間を空け、書類や事業実態を整えてから再チャレンジするのが基本です。
ネット銀行・地銀・信用金庫など選択肢を広げて検討する
メガバンクで断られたからといって、すべての銀行に拒否されるわけではありません。
ネット銀行は利便性重視、地方銀行や信用金庫は地域性や事業の実態を重視するなど、それぞれ特色や審査の着眼点が異なります。
私が支援した法人でも、メガバンクでは断られたものの、地域の信用金庫ではオフィスを直接訪問してもらい、事業の実態を確認して開設に至ったケースがありました。
銀行ごとに評価基準が違うため、複数の選択肢を検討することが合理的です。
落ちた理由を把握してから再申し込みするのが成功の近道
再申請で最も大切なのは「なぜ落ちたのか」を明確にすることです。
書類不備なのか、住所や事業内容への懸念なのかを整理しないまま別の銀行に申請しても、同じ理由で断られる可能性が高いのです。
私がサポートした一例では、最初の申請時に「契約書や取引実績が不足していた」ために断られました。
その後、契約書や請求書を揃えて再申請したところ、問題なく審査を通過しました。
つまり、落ちた理由を改善できるかどうかが、次の成功の分岐点になります。
審査に通りやすい銀行の特徴|メガバンク・ネット銀行・地銀の比較
口座開設の難易度は銀行の種類によって異なります。
「どこに申し込むか」で結果が変わるのは事実であり、同じ法人でもメガバンクでは断られ、地銀や信用金庫では通ることも珍しくありません。
私自身、公認会計士・税理士として多くの法人設立や資金管理を支援してきましたが、銀行ごとの特徴を理解して申請するかどうかで、開設のスピードや成功率は大きく変わります。
以下、それぞれの銀行の特徴を紹介します。
メガバンクは信用力を重視し審査は最も厳しい
三菱UFJ・三井住友・みずほといったメガバンクは、社会的信用が非常に高いため、その分審査は厳格です。
特に設立直後の法人や、事業の実態が不明確な会社は通りにくい傾向があります。
私の顧問先でも「将来的に取引規模が大きくなるからメガバンクにしたい」という相談を受けますが、実績がない段階では断られることが多いです。
そのため、スタートアップ期には別の金融機関で口座を作り、ある程度の事業実績を積んでからメガバンクに再申請する、という二段階の戦略を取るケースが実務上有効です。
ネット銀行は利便性重視だが書類不備にシビア
ネット銀行は「来店不要」「手続きが早い」など利便性が高い一方、非対面ゆえに提出書類の正確性を厳格にチェックします。
入力内容と登記簿や契約書の情報が少しでも矛盾していると、即座に審査落ちとなるケースもあります。
私が関与した法人では、登記簿に記載された表記と申請書の社名表記が微妙に異なっただけで差し戻しとなった例もありました。
つまり「利便性=通りやすさ」ではなく、「オンラインだからこそ形式にシビア」と理解して準備する必要があります。
地銀・信金は地域密着で事業の実態を重視する
地方銀行や信用金庫は、地域に根差した取引を大切にしており、審査の着眼点も「事業の実態があるか」「地域経済にどう貢献するか」にあります。
書類審査に加えて、代表者との面談やオフィス訪問で確認することもあります。
実務経験でも「メガバンクでは断られたが、地元の信用金庫では実際にオフィスを訪問して事業の説明をしたことで無事開設できた」という例がありました。
地域金融機関は融資や取引の将来性も含めて判断してくれるため、特に中小企業やスタートアップにとっては心強い存在です。
銀行が見るオフィス・事業の実態とは?法人口座開設で断られないための注意点
銀行が法人口座の審査で重視するのは、登記上の存在だけでなく「実際に事業が動いているか」です。
特に、オフィスや事業実態の確認は、マネーロンダリングや不正利用を防ぐ観点から強化されており、設立直後の法人やバーチャルオフィス利用企業は要注意です。
以下、私が公認会計士・税理士として支援してきた事例を交えながら、銀行がチェックする具体的なポイントを解説します。
オフィスの実在性と事業活動の有無が審査の焦点
銀行にとって、オフィスが実在し事業活動が行われているかは最初の判断基準です。
登記住所がバーチャルオフィスやシェアオフィスであっても、利用実態を証明できれば必ずしも不利ではありません。
私が支援したクライアントでも、シェアオフィスを利用していましたが、実際に執務スペースを使用していることを示す契約書や写真を提示したことで、問題なく口座が開設できました。
要は「住所と事業がリンクしていること」を伝えられるかどうかです。
電話・郵便物の受け取りなど日常的な事業運営が確認される
オフィスの存在だけでなく、日常的な業務が行われているかもチェック対象です。
具体的には、電話が通じるか、郵便物が受け取れるか、事務所に担当者が常駐しているかといった点です。
過去に、電話番号が連絡不能だったために追加確認を求められたケースもありました。
銀行にとっては「いつでも連絡でき、郵送物が届く会社かどうか」が重要な信頼の材料となります。
実際に稼働しているかを示す証拠資料が決め手になる
銀行は書類だけでは判断できない部分を「証拠資料」で確認します。
オフィス外観や執務スペースの写真、請求書や納品書、さらには会社案内やWebサイトといった外部に公開されている情報も有効です。
私の経験では、設立間もない法人が「最初の取引先との契約書・請求書」を提出したことで、実績が乏しいにもかかわらず審査を通過した例がありました。
また、登記書類以外に「契約書」などの追加書類を提出させられるのは、どこの銀行でも共通しています。
※私も法人口座開設時には、追加書類の提出を求められました。
「実際に事業が稼働している」ことを視覚的かつ客観的に示すことが、最後の一押しになります。
犯罪収益防止法で法人口座審査は厳格化|断られるリスクが高まる背景
ここ数年、法人口座の開設審査は以前より厳しくなっています。
その背景にあるのが「犯罪収益移転防止法(犯収法)」です。
マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために、銀行には本人確認や取引モニタリングの強化が義務付けられています。
結果として、法人にとっては「ちょっとした不備でも口座を断られる」状況が生まれています。
私自身、会計士・税理士として企業の口座開設を支援する際やクライアント監査の現場で、この法律の影響を肌で感じる機会が増えています。
以下、その具体的なポイントを整理します。
マネーロンダリング対策で本人確認が強化されている
犯収法の強化以降、銀行では代表者や取引担当者の本人確認が年々徹底されるようになっています。
昨今、オンラインカジノや暗号資産を利用した資金洗浄を背景に、各国でAML規制が強化され、銀行や事業者には資金源確認や非対面取引のモニタリングなど厳格な対応が求められています。
そのため、銀行口座開設においても、運転免許証やマイナンバーカードといった基本書類に加え、住所や連絡先の裏付け資料(住民票や公共料金の領収書など)を求められるケースも増えています。
私が支援した法人でも、申請書の住所と本人確認書類の住所が一致していなかったことで審査がストップした例がありました。
こうした小さな不一致も、銀行から見ればリスク要因となります。
このように、法人口座開設のためには、「本人確認資料は最新かつ完全に一致しているか」が重要です。
疑わしい取引の届出義務により銀行が慎重になっている
銀行には「疑わしい取引を検知した場合は当局へ届出する義務」が課されています。
そのため、事業内容が分かりにくい法人や、資金の流れが不透明な申請には慎重にならざるを得ません。
実際、私の支援先でも「資金移動が海外と頻繁に行き来する」という理由で追加説明を求められたケースがありました。
契約書や送金の目的を明確に提示したことで最終的には承認されましたが、説明できなければ即座に否認されてもおかしくない状況でした。
フィンテックやオンライン取引増加でリスク監視が強化
キャッシュレス決済やフィンテック事業の広がりにより、銀行は従来以上にリスク監視を強化しています。
非対面取引やオンライン決済は便利な一方、不正利用の温床になる可能性があるため、法人口座開設の段階から厳しく審査されます。
私の関与したスタートアップでも、オンライン完結型のサービスを展開していたため、事業実態の説明資料(サービス概要書や利用規約)を追加提出することで審査をクリアしました。
このように、新しいビジネスほど、従来の審査基準にない部分をどう説明するかが鍵になります。
「法人口座開設審査がゆるい」と言われる銀行口座は本当にあるのか?
ネット上では「法人口座開設審査がゆるい銀行」「簡単に作れる口座」といった情報を目にすることがあります。
確かに、手続きの簡便さや提出書類の少なさ、面接不要といった点が、「ゆるい」「簡単に作れる」という一つの指標になります。
しかし、手続はゆるくても、実務の現場を見てきた経験から言えば「特別に甘い審査」は存在しません。
あるのは銀行ごとに審査の着眼点や運用の仕方が違うだけです。
以下、その実態を整理しつつ、どうすれば審査通過率を高めることができるのかを解説します。
審査通過率で「法人口座開設審査がゆるい銀行」はない|手続きの簡便さは別問題
「法人口座開設審査がゆるい銀行」という表現を目にすることがありますが、審査通過率という観点で見ると、そのような審査が甘い銀行は存在しません。
銀行はすべて、犯罪収益移転防止法などの法令に基づき、本人確認や事業実態の確認を行う義務を負っているため、基準自体は共通化されているからです。
一方で、「ゆるい」と言われる背景には、手続き面の違いがあります。
ネット銀行ではオンライン完結で来店が不要だったり、地域金融機関では担当者との面談を通じて柔軟に対応してもらえたりと、「手続きの簡便さ・やり取りのしやすさ」に差があるのは事実です。
私が法人口座開設を支援した際も、メガバンクでは審査落ちになったものの、同じ内容で信用金庫に申請したところ、担当者がオフィス訪問を行い、実態を確認したうえで口座開設に至ったケースがありました。
これは「審査がゆるい」のではなく、基本的な審査基準は同じでも確認の仕方やサポートの仕方が異なる結果といえます。
つまり、「審査通過率が高い銀行=審査がゆるい銀行」ではありません。
大切なのは、どの銀行に申し込むかよりも、必要書類を正確に揃え、事業の透明性を示す準備をしているかです。
銀行ごとに重視する審査ポイントが異なるだけ
銀行に共通の基準がある一方で、各銀行がどこを特に重視するかは違います。
- メガバンク:企業の信用力や事業規模を重視
- ネット銀行:書類や入力情報の正確性を厳格にチェック
- 地銀・信金:地域とのつながりや実態確認を重視
例えば、私が支援した企業ではメガバンクで断られましたが、信用金庫で代表者面談とオフィス訪問を経て開設できました。
これは「審査がゆるい」のではなく「評価軸が異なる」ために生じた差です。
結論:審査を通すには書類の正確さと事業の透明性が最重要
結局のところ、銀行の種類にかかわらず重要なのは「必要書類に不備がないこと」と「事業の実態が明確であること」です。
登記簿と本人確認資料の一致、契約書や請求書による事業の説明が整っていれば、銀行に安心感を与え、審査はスムーズになります。
私自身、複数の銀行で断られた法人を支援した際、最終的に通ったのは「書類を徹底的に整備し、事業を透明に見せられたから」でした。
このように、審査に通るかどうかは銀行選びよりも準備の精度に左右されるのです。
法人口座開設を断られる理由に関するよくある質問・回答
法人口座開設を断られる理由に関するよくある質問・回答をまとめました。
法人口座開設ができない理由は何ですか?
代表的なのは、以下のケースです。
- 事業実態が不明確
- 登記住所と実際の活動場所が一致しない
- 本人確認資料や書類に不備がある
私の経験でも「契約書や請求書がない」といった理由で断られる法人が多くあります。
法人口座が作れない場合、どうすればいいですか?
まずは落ちた理由を把握し、書類や説明を補強することが重要です。
そのうえで、ネット銀行の法人口座や信用金庫など申請先を変えてみると通ることもあります。
実務では「信用金庫での面談を経て開設できた」という例もありました。
審査がゆるい法人銀行口座は?
「審査がゆるい銀行」は存在しません。
犯罪収益防止法により、銀行間で基準は共通化されています。
ただし、手続きの簡便さ(オンライン完結や来店不要)で法人口座開設審査がゆるい銀行はあります。
重要なのは、必要書類を整え事業の透明性を示すことです。
口座開設の審査が厳しいのはなぜですか?
マネーロンダリングや不正利用を防ぐため、銀行はリスク管理を徹底しています。
特にオンライン取引や海外資金移動が増える中、本人確認や事業確認は以前より厳格になっています。
実際に監査の現場でも、その影響を強く感じることが増えています。
法人口座を作れないとどうなる?
取引先からの信用を失うだけでなく、決済や資金管理ができず事業運営に支障をきたします。
また、資金の受け皿がないと融資や補助金の申請も難しくなります。
過去に「個人口座で代用していたが、取引先に不安視され契約を失った」事例も見てきました。
【比較表】おすすめの法人口座
おすすめの法人口座の比較表は、下表のとおりです。
| GMOあおぞらネット銀行 | 三井住友銀行Trunk | 住信SBIネット銀行 | PayPay銀行 | 楽天銀行 | りそな銀行 | ゆうちょ銀行 | みずほ銀行 | 千葉銀行 | 関西みらい銀行 | SBI新生銀行 | 横浜銀行 | 城南信用金庫 | 福岡銀行 | 三菱UFJ銀行 | イオン銀行 | セブン銀行 | ローソン銀行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  | ||||||||||||||||
| 総合評価 | ( 9.7点 ) | ( 9.6点 ) | ( 9.6点 ) | ( 8.4点 ) | ( 8.1点 ) | ( 7.7点 ) | ( 7.3点 ) | ( 7.0点 ) | ( 6.6点 ) | ( 6.6点 ) | ( 6.6点 ) | ( 6.4点 ) | ( 6.4点 ) | ( 6.3点 ) | ( 6.0点 ) | ( 5.9点 ) | ( 5.3点 ) | ( 5.1点 ) |
| 書類提出方法 | web完結 | web完結 | web・郵送 | 郵送 | 郵送 | web完結 | 店頭窓口 | web・郵送 | 店頭窓口 | web・郵送 | 店頭窓口 | web完結 | 店頭窓口 | web完結 | web完結 | 店頭 | 非公開 | 郵送 |
| 口座開設スピード | 最短即日 | 最短翌営業日(※1) | 最短翌日 | 最短3日 | 約2週間 | 約2週間 | 約1ヶ月 | 1~2週間 | 最短数日 | 約1週間 | 約2週間 | 2~3週間 | 1~2週間 | 1~2週間 | 1ヶ月以上 | 3週間 | 非公開 | 2週間程度 |
| 店頭手続 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 | 非公開 | 不要 |
| 振込手数料 (同行宛て) | 無料 | 無料 | 無料 | 55円 | 無料 | 330円 | 100円 | 0~440円 | 0~330円 | 0~330円 | 無料 | 0~330円 | 0~220円 | 0~110円 | 110~330円 | 無料 | 55円 | 55円 |
| 振込手数料 (他行宛て) | 129~143円 | 一律145円 | 130~145円 | 160円 | 150~229円 | 605円 | 165円 | 490~660円 | 385~550円 | 605円 | 220~550円 | 385~550円 | 264~440円 | 330~550円 | 484~660円 | 150~229円 | 165円 | 143円 |
| 口座維持費用 (ネットバンキング) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3,300円~ | 550円~ | 5,500円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 1,100円~ | 2,200円 | 1,100円~ | 1.430円~ | 1,760円 | 2,200円 | 6,600円 | 無料 |
| 社会保険料口座振替 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 |
| 労働保険口座振替 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 |
| 公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
※注釈
- 振込手数料は1回あたりの金額
- GMOあおぞらネット銀行の振込手数料は「振込料金とくとく会員(月額500円)」だと129円で利用可能
- 住信SBIネット銀行の振込手数料は、前々月の振込回数に応じて最大130円まで引き下げ可能
- 口座維持費用(ネットバンキング利用料)は1ヶ月あたりの金額
- ゆうちょ銀行やメガバンクなどのネットバンキング利用料は、別途契約料が取られます
- 上記比較表は基本情報を掲載していますが、法人の状況等によって条件が変化する場合があります
- 定量的に測れない指標については、アンケート調査・データ分析などの相対評価による
- 口座振替やダイレクト納付については、以下のサイトを参照
・日本年金機構「厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表」
・国税庁「利用可能金融機関一覧(ダイレクト納付)」
・厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
(※1)三井住友銀行Trunkの最短翌営業日の開設は、以下の条件を満たす必要がある。
- 取引責任者と代表者が同一であること
- スマホによる本人確認認証を行い、必要書類をアップロードすること
- 当日中にマイナンバーカードによる本人確認認証や必要書類アップロードを行うこと
- Web面談の予約を申込日の翌営業日に実施すること



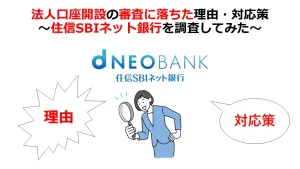
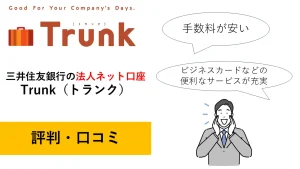


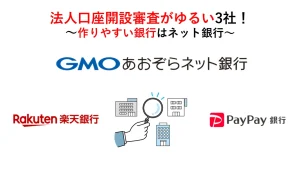


コメント