「不動産担保ローンはやばいのでは?」と不安に思う方は多いでしょう。
確かに、不動産を担保にする以上、返済が滞れば住まいや事業の拠点を失うリスクがあり、契約内容をよく理解せずに利用すれば深刻なトラブルに発展する可能性があります。
一方で、正しく利用すれば無担保ローンでは得られない大きなメリットも享受できます。重要なのは、メリットとデメリットを比較したうえで、自分に合った使い方を見極めることです。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 借入可能額 | 担保があるため高額の借入が可能(数千万円規模も可) | 借りすぎると返済不能時のリスクが大きい |
| 金利水準 | 無担保ローンより低金利で借りられる傾向 | 高金利を提示する悪質業者も存在 |
| 返済期間 | 長期返済が設定でき、月々の負担を軽減しやすい | 長期化により総返済額が膨らむ可能性 |
| 審査の通りやすさ | 不動産の価値で評価されるため、信用情報に不安があっても通る場合あり | 審査が甘い業者ほど返済条件が厳しく、リスクが増す |
| 資金用途の自由度 | 事業資金・生活資金・借換えなど幅広く利用可能 | 目的が不明確だと資金が浪費され、返済に困るケースあり |
| 担保リスク | 不動産を有効活用できる | 返済不能時には不動産を失い、生活・事業基盤を喪失する恐れ |
| 保証人の要否 | 不動産価値が十分なら保証人不要のケースもある | 不足分を補うために連帯保証人を求められる場合がある |
本記事では、私の公認会計士・税理士としての実務経験をもとに、「やばい」と言われる理由や不動産担保ローンのデメリット、実際に起こりやすいトラブル事例を解説します。
また、正しい利用方法や安全に選ぶためのポイント、さらにおすすめの不動産担保ローンまで紹介します。
読後には、不動産担保ローンのリスクを理解しつつ、安心して活用できる判断基準を得られるはずです。
1988年生まれ
公認会計士・税理士
2014年 EY新日本有限責任監査法人 入所
2021年 ニューラルグループ株式会社 入社
2022年 株式会社フォーカスチャネル取締役 就任
2024年 太田昌明公認会計士・税理士事務所 開業
2024年 ARMS会計株式会社 代表取締役社長
2025年 東京税理士会向島支部 幹事(役員)【税務支援対策部】
前職では上場会社の経理財務部長として勤務し、現在は経理・財務支援サービス会社を経営しています。
財務担当として銀行取引経験があり、メガバンク・地方銀行・日本政策金融公庫などの対応をしていました。これまでに取り扱った融資規模は、1件あたり1,000万円~10億円です。
また、不動産業界の会計監査に携わっていたので不動産業界の知見(減損会計による不動産の収益性の計算・判定・時価評価、SPCのスキーム・ローン検討等)や、不動産賃貸業(賃貸事業所・オフィス・クリニック向け)の経営のサポート(主に経理・税務申告対応)経験を活かし、不動産担保投資・不動産担保ローン全般の相談も受けております。
なぜ「不動産担保ローンはやばい」と言われるのか?背景にある3つの理由
「不動産担保ローンはやばい」と言われる大きな理由は、次の3つです。
不動産担保ローンは「大きな資金を調達でき、金利も比較的低い」「無担保ローンより審査通過しやすい」というメリットが強調されがちです。
しかし、私の実務経験からすると、安易に利用してしまうと後戻りできない深刻な問題に直面するケースも少なくありません。
特に、無担保ローンと比べてのリスク、金融機関による審査基準・融資条件の差、そして借入額の大きさが生む返済不能リスクは、多くの相談現場で繰り返し目にしてきた落とし穴です。
以下、それぞれ「不動産担保ローンがやばい」と言われる理由を解説します。
無担保ローンと比べてリスクが大きいと言われる理由|不動産を失うリスク
無担保ローンの場合、万が一返済できなくなっても「信用情報への傷」が主な影響にとどまります。
もちろん信用情報の悪化は大きなマイナスですが、生活の基盤となる不動産を直接失うわけではありません。
一方で、不動産担保ローンは返済が滞れば、担保として差し入れた自宅や事業用不動産を失うリスクが現実のものとなります。
当社に相談された方の中にも、事業の資金繰りのために利用したものの、売上不振で返済が遅れ、結果として事業所を手放さざるを得なくなったケースがありました。
「生活や事業の拠点を担保にする」という点で、不動産担保ローンは無担保ローンよりも一段階リスクが大きいと言えるのです。
金融機関によって審査基準や条件に大きな差がある|返済予定が破綻する可能性
不動産担保ローンは「不動産があれば借りられる」と思われがちですが、実際には金融機関ごとに審査基準が大きく異なります。
同じ物件でも、ある銀行では高評価がつき、別のノンバンクでは低評価になることもあります。
さらに、金利や返済期間、必要書類の範囲にも大きな違いがあり、借入条件の不一致が返済計画を破綻させる要因となります。
特に私が過去に支援した案件では、金融機関から提示された条件が「当初の想定より返済期間が短い」ために毎月の返済負担が急増し、キャッシュフローが逼迫する事態に陥った事業者もいました。
審査基準から来る「融資条件」を軽視すると、「借りられること」に安心してしまい、その後の返済が続かなくなるのです。
借入額が大きい分だけ返済不能のダメージが重い
不動産担保ローンは、通常のカードローンや事業者ローンよりも高額な融資が可能です。
そのため、成功すれば大きな資金調達効果がありますが、失敗した場合のダメージも比例して大きくなります。
例えば、数百万円のカードローン返済が滞った場合でも、最悪のケースは信用情報の傷と差し押さえに限られます。
しかし、不動産担保ローンでは数千万円規模の借入れを行うことが多く、返済不能になれば不動産売却に加えて追加の債務が残ることもあります。
私が(手遅れの状態で)相談を受けたケースでも、借入額が大きすぎたために「不動産を失ってもなお借金が残る」という深刻な事態に陥った事例もありました。
つまり、借入額の大きさがもたらすリスクは、単なる返済不能以上に重い負担を背負わせるのです。
実際に起きやすいトラブル事例と借り手が直面するリスク
実際に起きやすいトラブル事例と借り手が直面するリスクは、以下の3つです。
不動産担保ローンの相談を受けていると、「借りられるかどうか」ばかりに意識が向き、契約後に直面するトラブルを想定していない方が多く見受けられます。
ところが、実際に起きやすい問題は借入後に発覚するケースがほとんどです。
以下、私が実務で見てきた代表的な3つのトラブル事例を紹介します。
不動産評価額が低く査定されるケース
「この物件なら3,000万円くらいの担保価値はあると思っていたのに、金融機関の評価は半分以下だった」という相談は珍しくありません。
不動産の評価額(担保としての価値)は市場価格ではなく、各金融機関の独自基準で決まるため、一般的な時価と乖離するケースもあります。
| 項目 | 市場価格(一般的な相場) | 金融機関の担保評価 | 低評価となる理由 |
|---|---|---|---|
| 一般的な土地・住宅 | 需要と供給で決まる取引価格 | 競売で売れる価格を基準に低めに算定 | 万一の換金性を重視するため市場価格より低め |
| 築年数が古い木造住宅 | まだ住める・リフォームすれば価値ありとされる | 建物はほぼ評価ゼロ、解体費用を差し引く場合も | 耐用年数が尽きていると見なされ、担保価値なし |
| 市街化調整区域の土地 | 広さや立地によっては需要あり | 再建築不可など利用制限で大幅に低評価 | 流動性が低く、担保処分でも売れにくいと判断 |
| 再建築不可の土地 | 個人売買では値が付くことも | 建物を建て替えられないため評価が極端に低い | 法規制により担保としての価値が限定される |
例えば、築年数が古い木造住宅や市街化調整区域内の土地は、市場ではそれなりの価値があるのに、金融機関の担保評価では大幅に低く見積もられがちです。
その結果、希望した融資額が出ず、資金計画が崩れてしまうことになります。
当社に相談があった例では、借り手が事業拡大のために担保を差し入れたところ、期待していた評価の7割しか認められず、追加の資金調達が必要になったことがありました。
事前に「どの金融機関がどう評価するか」を複数比較することが、計画倒れを防ぐ鍵になります。
返済遅延による担保不動産の処分リスク
返済が滞ると、金融機関は担保権を実行し、最終的に不動産の競売や任意売却に進むことがあります。
特に怖いのは、数回の延滞でも金融機関から厳しい催告が届き、心理的に追い込まれる点です。
借入の返済が遅れると、金融機関や貸金業者からの督促は段階的に強まっていきます。
最初に届くのは、滞納からおおむね1週間以内に送付される督促状です。この段階では「今月分の返済が確認できていません」といった比較的穏やかな文面で、速やかな入金を求められます。
しかし、ここで対応を怠ると、1週間から1ヶ月ほどの間に新たな督促状や電話連絡が繰り返され、その内容も次第に厳しい調子へと変化していきます。
さらに返済を放置し続けると、1~2ヶ月程度で「元金」「利息」に加えて「遅延損害金」を請求する通知が届くようになります。
実際、私が話に聞いたことがある事例だと、数ヶ月の返済遅延で競売の申立てを受け、慌てて資金繰りを整えたものの、裁判所の手続きが進行していたため回避できなかったというケースがあります。
結果的に、事業用物件を失い、事業自体を縮小せざるを得なくなったのです。
「延滞してもすぐには取り上げられない」という誤解を持つ方は少なくありませんが、金融機関は契約に基づいて迅速に動きます。
小さな遅延でも早めに対応することが何より重要です。
名義や共有者の同意をめぐるトラブル事例
不動産担保ローンを組む際、物件の名義が単独所有ではなく共有の場合、全員の同意が必要になります。
ここで同意が得られず、契約が進まないというトラブルは現場で頻発します。
例えば、親子で共有している不動産を担保にしようとした場合、子どもが同意を拒否すればローンは成立しません。
さらに、相続した不動産で共有者が複数いる場合、全員と連絡を取り合うのは現実的に難しく、結果として融資の話が頓挫することもあります。
私自身、相続の相談事例で、共有状態になっていた土地を担保にしたいという相談を受けた際、遠方に住む相続人の一人が「リスクが怖い」と首を縦に振らず、借入が不可能になった例を目の当たりにしました。
このように、不動産担保ローンにおける「名義や同意」の問題は、単なる手続き上の形式ではなく、家族関係や相続人同士の感情が色濃く影響します。
そのため、共有不動産を担保に考えている方は、金融機関との交渉以前に、まずは関係者間で合意形成を図ることが欠かせません。
トラブルを未然に防ぐには、専門家を交えて早い段階から調整を進めておくことが、最も現実的で安心な解決策といえるでしょう。
審査が甘い不動産担保ローンに潜む落とし穴
審査が甘い不動産担保ローンは上手く使えば大変便利なサービスですが、使い方を一つ誤ると落とし穴に足を取られることになります。
「審査が甘い」という言葉に魅力を感じてしまうのは自然なことです。
特に急ぎで資金が必要なときや、他で断られた経験がある人にとっては心強いでしょう。
しかし、私の事務所に寄せられる相談の中には、リスクとメリットを正しく比較できずに「審査が甘い=安心」と誤解し、実際には「審査が甘い=リスクもある」と気づいたときには後悔している方が少なくありません。
ここでは、その代表的な落とし穴を、以下の3つの視点から解説します。
「誰でも借りられる」という宣伝の裏側
インターネットや広告で「誰でも絶対に借りられる不動産担保ローン」「審査なしで即融資」などと謳っている業者があります。
しかし、その実態を確認すると、法外な条件を隠しているケースが多いのです。
例えば、「融資はすぐに可能です」と言いながら、契約書をよく読むと担保評価額の8割ではなく5割程度しか貸さず、その差額に見合わない高い手数料を課していることもあります。
私が過去に被害相談を受けた案件では、「個人向け即日融資」を掲げる業者と契約したものの、実際には融資額が大幅に少なく、結果として追加融資を繰り返し依頼せざるを得なくなり、借入総額が膨れ上がった例もありました。
つまり、「誰でも借りられる」という言葉の裏には、借り手側にとって不利な条件が潜んでいることを常に疑うべきです。
高金利・短期返済を迫られるケースがある
審査が甘いローンは、金融機関にとって「回収リスクが高い融資」です。
そのリスクを補うために設定されるのが、高金利や極端に短い返済期間です。
例えば、通常の不動産担保ローンが年利3〜8%程度であるのに対し、審査が甘い業者の場合は15%近い水準(※)を提示することもあります。
※ただし、法定利息内で違法ではない(参考:日本貸金業協会『お借入れの上限金利は、年15%~20%です』)
さらに、契約内容によっては、返済期間も10年・15年ではなく、数年での一括返済を求められる場合があります。
私が以前に相談を受けた中小企業の経営者は、「借りやすさ」だけを理由に契約した結果、想定よりも短期間での返済を迫られ、資金繰りが一層悪化しました。
結局、別の金融機関から追加の融資を受けざるを得ず、借金の連鎖に陥ったのです。
「借りやすさ」と「返しやすさ」は別物であるという点を、必ず押さえておく必要があります。
業者の中には、「担保を取り上げる(不動産を取得して、売り捌く)」ことを主目的としている貸金業者もいますので、中小の聞き慣れない業者から借入する際には、十分な注意が必要です。
不安な方は、大手の「セゾンファンデックス」「AGビジネスサポート」を利用すると良いでしょう。
審査が甘いほど返済条件が厳しくなる理由
審査が甘い金融機関や業者は、借り手の信用を精査しない代わりに、担保や返済条件で強く縛る傾向があります。
具体的には、以下のような特徴があります。
- 担保評価を低めに設定して、融資額を抑える
- 遅延損害金を通常より高く設定する
- 少しの返済遅延で担保権を実行する
私が経験したケースでも、ある業者は「審査が早い」と宣伝していましたが、契約書には「1回の延滞で担保権を即実行できる」との条項が盛り込まれていました。
借り手は「普通は数回の滞納で督促が来るはず」と思っていたため、1度の遅延で担保を失う事態になり、大きなトラブルとなりました。
※実際には、トラブルが生じた場合でも裁判所や監督当局の判断によって制限されることはありますが、その際には高額な弁護士費用を負担し、裁判で争わざるを得なくなるケースが少なくありません。
つまり、審査が甘いということは、金融機関がリスクを抱える分、それを借り手の不利な条件で補おうとする構造になっているのです。
悪質業者を見抜くポイント|安全に借りるためのチェックポイント
悪質業者を見抜くポイントは、次の3つです。
不動産担保ローンを検討する際、最も注意しなければならないのが「業者選び」です。
金利や返済条件だけで比較してしまうと、後から思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
ここでは、悪質業者を見抜くために特に重要な3つの視点を解説します。
過去の行政処分歴や口コミの確認|当社が調査したデータも紹介
悪質な業者は、過去に金融庁や都道府県から行政処分を受けているケースが少なくありません。
金融庁公式サイトの「金融サービス利用者相談室」や「行政処分事例集」、東京都産業労働局「行政処分を受けた業者|貸金業」などから過去の処分歴を調べることが可能です。
※各都道府県が公表する処分事例は、Google検索から「●●県 貸金業 処分」で検索することが可能です。
また、実際に利用した人の口コミや評判も重要な情報源です。
ただし、インターネット上の口コミは自作自演のケースもあるため、「一方的に良い評価ばかり」あるいは「極端に悪い評価ばかり」の場合は注意が必要です。
私の経験上、悪質な行政処分歴がある業者は契約条項や返済管理の厳しさに問題を抱えていることが多く、顧客トラブルに発展する割合が高い印象を受けます。
当社では、各社の評判・口コミやおすすめの不動産担保ローン業者を紹介していますので、こちらもご参考にして下さい。
契約書に不透明な条項がないかチェック
悪質業者の特徴の一つは、契約書に借り手に不利な条項を紛れ込ませていることです。
たとえば、以下のような内容が記載されていないか注意してください。
- 「1回の延滞で担保権を即時実行できる」
- 「解約手数料」「管理費用」など名目不明の費用が多い
- 遅延損害金が法定上限(年20%)を超えて記載されている(利息制限法7条)
私が関与した相談の中には、契約書に小さな文字で「担保権実行は業者の裁量による」と書かれていたケースがありました。
借り手は十分に理解しないまま契約してしまい、返済遅延が発生した途端に強制的に担保不動産を処分される事態に陥ったのです。
契約書の条項を一つひとつ丁寧に確認し、不明点があれば必ず専門家に相談することが不可欠です。
正規登録業者かどうかを見極める方法
不動産担保ローンを扱うには、貸金業法に基づく「貸金業登録」が必要です。
金融庁や東京都などの各都道府県の公式サイトには、正規に登録された業者のリストが公開されています。
※Google検索から「●●県 貸金業者登録」等で検索することが可能です。
契約を検討する際には、必ず業者名を照会し、登録番号を確認してください。
過去には、無登録で営業している「ヤミ金融」が不動産担保ローンを装って勧誘する事例もありました。
こうした業者は高金利や違法な取り立てを行い、トラブルが発生しても法的な救済を受けにくいという危険があります。
私の事務所に相談に来られた方の中には、「ネット広告で見つけた業者」と契約しようとしたところ、調べてみると登録がなく、危うくヤミ金融と契約する寸前だった例もありました。
返済できなくなったらどうなる?担保不動産を失うリスクの実態
不動産担保ローンは「借りやすい」「高額を借りられる」といった利便性が強調されますが、返済が滞ったときのリスクは想像以上に大きいものです。
実際の相談現場では、返済不能が数ヶ月続いただけで、生活や事業の基盤そのものを失ってしまう方もいます。
ここでは、返済できなくなった場合に起こる現実を具体的に解説します。
任意売却や競売に至るプロセス
返済が数ヶ月以上滞ると、金融機関は担保権を実行するために動き出します。
最初に行われるのが「任意売却の打診」です。
任意売却とは、住宅ローンや不動産担保ローンの返済が困難になった場合に、債務者(借り手)が債権者(金融機関など)の同意を得て担保不動産を売却し、その売却代金をローンの返済に充てる手続きを指します。
市場に近い価格で売却できる可能性があるため、競売よりはダメージが小さくなるケースもあります。
しかし、任意売却で買い手が見つからなければ、最終的に裁判所を通じた「競売」に進みます。
競売は短期間で処分されるため、市場価格の7割程度、場合によっては半額以下で落札されることも珍しくありません。
私が相談を受けた中小企業のオーナーは、返済遅延からわずか半年で競売に至り、実勢価格の半分ほどで事業用不動産を失いました。
返済を先延ばしにすることが、結果的に大きな損失を招く典型例です。
連帯保証人への影響と責任の範囲
不動産担保ローンでは、借り手本人だけでなく「連帯保証人」を立てることが求められるケースがあります。
連帯保証人は「借り手と同じ責任」を負うため、返済が滞れば保証人にも一括で請求が及びます。
私の事務所でも、経営者が法人で借入をした際、奥様を連帯保証人にしていたケースがありました。
返済が滞った結果、担保不動産を処分した後も借金が残り、連帯保証人である奥様に請求が行われ、家庭全体が経済的に追い込まれてしまいました。
連帯保証は「名前だけ貸す」ものではなく、借金そのものを一緒に背負う行為であることを、借り手と保証人双方が理解しておく必要があります。
(参考)保証人と連帯保証人の違い
| 項目 | 通常の保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 債務の責任範囲 | 借主が返済できない場合に限り、補助的に返済義務を負う | 借主と同じ立場で、全額の返済義務を負う |
| 請求の順序 | 「まず借主に請求してほしい」と主張できる(催告の抗弁権あり) | 催告の抗弁権なし → 債権者はいきなり連帯保証人に請求可能 |
| 借主の財産調査 | 「借主の財産から先に差し押さえてほしい」と主張できる(検索の抗弁権あり) | 検索の抗弁権なし → 借主に財産があっても、保証人から直接回収される可能性あり |
| 責任の重さ | 補助的な責任にとどまる | 借主と同等の責任を負う(ほぼ共同債務者に近い立場) |
家族が住んでいる場合の生活リスク
担保に差し入れた不動産が自宅である場合、返済不能は「住まいを失う」ことを意味します。
金融機関は情状を酌量してくれるわけではなく、競売や任意売却が進めば家族は退去を迫られます。
実際、私の知り合いの税理士が相談を受けたご家庭では、ローンの返済が滞ったことで自宅が競売にかけられ、小さなお子さんがいる中で急な引っ越しを余儀なくされました。
借金の問題が、生活の安定や家族の精神的な安心に直結することを痛感した事例です。
「返せなくなったら家を失うかもしれない」という現実は、広告や営業トークではあまり強調されません。
しかし、担保不動産が生活の拠点である場合、このリスクは最も重大な問題になります。
安全に利用するために知っておくべき契約前の確認ポイント
不動産担保ローンは大きな資金を調達できる便利な仕組みですが、契約前に確認すべきポイントを見落とすと後悔につながります。
実際、私の事務所に相談に来られる方の多くが「借りること」だけに意識が向いてしまい、「返せるのか」「他に方法はなかったのか」という視点を欠いたまま契約してしまっています。
ここでは、安全に利用するために特に大切な3つの視点を紹介します。
借入目的と返済計画を明確にする重要性
不動産担保ローンは金額が大きい分、「何のために借りるのか」「どのように返すのか」を曖昧にしたまま契約すると危険です。
例えば、事業資金として借りるのであれば、資金の投入先と回収見込みを数字で落とし込む必要があります。
生活資金の補填目的であれば、安定した収入源が確保できているかを冷静に確認しなければなりません。
私が支援した経営者の中には、借入の目的が不明確なまま資金を使い始め、結果的に「どこに使ったのか」が曖昧になり返済原資が確保できなかった例もあります。
借入目的と返済計画を紙に書き出して整理するだけでも、安易な判断を防ぎ、契約後の安心感につながります。
他の資金調達手段との比較検討
「不動産担保ローンは絶対に借りられる」と思い込んでしまう方は多いですが、実際には他の選択肢もあります。
ビジネスローンやファクタリング、信用保証協会付き融資など、状況によっては不動産を失うリスクを伴わずに資金を確保できる手段があります。
私自身、相談を受けた際には「本当に不動産担保ローンでなければならないのか」を必ず確認します。
中には、短期的な資金不足であれば売掛債権を活用したファクタリングの方が合理的な場合もありますし、法人であれば補助金や助成金を組み合わせる方が安全なケースもあります。
不動産担保ローンは強力な資金調達手段ですが、「最善」ではなく「最後の選択肢」にすべき場面もあることを理解しておくべきです。
契約前に専門家へ相談するメリット
契約書の条項や返済条件は、一般の方にとって分かりづらいものです。「この条件は普通なのか」「不利な条項は隠れていないか」といった点は、金融実務に精通していないと判断が難しいのが実情です。
私が過去に対応したケースでは、契約書に「1回の延滞で担保権を実行可能」と記載されており、借主は「そんなに厳しいとは思わなかった」と後から驚いていました。
もし契約前に専門家へ相談をしていれば、そのリスクを事前に指摘されたハズです。
実際に私がマネジメントインタビューに同席したM&A支援の場面でも、オーナーが「借入は完済したので抵当権は外れていると思っていたが、根抵当権は抹消登記をしなければ残ったままだとは知らなかった」と驚きと落胆を口にされたことがありました。
※その際には、速やかに金融機関から「根抵当権抹消同意書」を受け取り、法務局で抹消登記を申請するようアドバイスしました。
このように、専門家へ相談することで、契約内容の妥当性を客観的に確認でき、他の資金調達手段との比較アドバイスも受けられます。
相談コストは発生しますが、それ以上に「不動産を失うリスク」を回避できる安心感を得られるのは大きなメリットです。
不動産担保ローンの正しい利用方法
不動産担保ローンは、リスクを理解せずに利用すれば「やばい」状況に陥ります。
しかし、事前に正しい準備をしておけば、安全に資金調達が可能です。ここでは、契約前に必ず実践すべき3つの行動を紹介します。
借入の目的を明確にし資金の使い道を必ず書き出す
まず大切なのは、「なぜ借りるのか」を自分自身に問い直すことです。
資金の使い道を曖昧にしたまま契約してしまうと、返済原資が確保できずに資金繰りが破綻するリスクが高まります。
具体的には、借入金を どの項目に、いつまでに、いくら充てるのか を書き出してみましょう。
事業資金なら「仕入れ・運転資金・設備投資」などの区分ごとに、生活資金なら「教育費・医療費・住宅費」など具体的に整理すると、借入が本当に必要かどうかが見えてきます。
私の支援経験でも、資金使途を明確化したことで「実は全額借入しなくてもよかった」と気づき、無駄な借金を回避できた方がいました。
一方、「お金に色は無い」として資金の使い道を曖昧にする人は、効率的に資金を動かしているように見えても、結果的に銀行の信頼を損ね、投資先の事業も伸びず、返済困難という深刻な局面に陥りがちです。
収入に基づいて返済シミュレーションを行い借入額を抑える
資金使途を明確にした後に重要なのは、返済計画をシミュレーションすることです。
借入可能額いっぱいまで借りられると安心に感じるかもしれませんが、返済は毎月の収入から行わなければなりません。
給与所得や事業収入、家賃収入など「安定して入ってくる金額」をベースにして、月々いくらなら返済できるかを計算してみましょう。
エクセルや金融機関の返済シミュレーションを使うのも有効です。
私が相談を受けたある経営者は、返済可能額を冷静に試算した結果、当初希望していた借入額の半分に抑えました。
その判断が功を奏し、数年後には無理なく完済できています。
「借りられる額」ではなく「返せる額」で判断することが、不動産を失わないための第一歩です。
契約前に必ず複数の金融機関を比較し条件を徹底的に確認する
最後に欠かせないのは、契約条件の比較です。
金利や返済期間、担保評価は金融機関によって大きく異なります。
1社の提示条件だけで即決するのは危険です。
最低でも2〜3社から見積もりを取り、条件を横並びで比較しましょう。
その際、金利だけでなく「返済期間」「繰上返済の可否」「遅延損害金の率」など細かい点まで確認することが重要です。
私が相談を受けたケースでも、最初に提示された条件は金利が高く返済期間も短いものでしたが、別の金融機関に相談したことで条件が大幅に改善し、オーナーの資金繰りに余裕が生まれました。
「どこから借りるか」で、その後の数年〜数十年の生活や事業が大きく変わります。
必ず複数の金融機関を比較する習慣を持ってください。
【比較表】おすすめの不動産担保ローン
以下、おすすめの不動産担保ローンの比較表です。
| セゾンファンデックス | AGビジネスサポート | 丸の内AMS | ファンドワン | トラストホールディングス | 日宝 | MIRAIアセットファイナンス | MRF | つばさコーポレーション | 総合マネージメントサービス | マテリアライズ | アサックス | JFC | アビック | デイリーキャッシング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | |||||||||||||||
| 総合評価 | ( 9.7点 ) | ( 9.6点 ) | ( 8.1点 ) | ( 7.8点 ) | ( 7.7点 ) | ( 7.1点 ) | ( 7.0点 ) | ( 6.7点 ) | ( 6.3点 ) | ( 6.1点 ) | ( 6.0点 ) | ( 6.0点 ) | ( 6.0点 ) | ( 6.0点 ) | ( 5.4点 ) |
| 金利 | 3.15~9.9% | 公式サイト参照 | 3.8~15% | 2.5~18% | 3.45~7.45% | 4~9.9% | 4~9.5% | 4~15% | 4~15% | 3.4~9.8% | 4.8~9.8% | ~7.8% | 5.86~15% | 2.98~15% | 5.2~13% |
| 融資速度 | 最短3日 | 最短3日 | 最短2日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短翌日 | 最短数日 | 最短即日 | 最短3日 | 最短翌日 | 最短3日 | 3日~1週間 | 最短2日 | 非公開 |
| 借入限度 | ~5億円 | 100万円~5億円 | ~5億円 | ~1億円 | ~10億円 | ~5億円 | ~5億円 | ~3億円 | 非公開 | ~5億円 | ~3億円 | ~10億円 | ~5億円 | ~50億円 | ~8,000万円 |
| 返済期間 | 5~25年 | ~30年(※1) | ~35年 | ~35年 | ~30年 | ~30年 | ~20年 | ~3年 | ~30年 | ~35年 | ~20年 | ~30年 | ~10年 | ~30年 | ~30年 |
| 保証人(※2) | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 可能性有 | 原則不要 |
| 抵当順位 | 不問 | ※3 | 不問 | 非公開 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 原則1位 | 不問 | 非公開 |
| 評判を見る | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ |
| 公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
※注釈
- (※1)元利均等返済:最長30年(360回以内)、元金一括返済:最長30年(360回以内)
- (※2)法人契約の場合は原則代表者の連帯保証が必要。担保提供者の連帯保証が必要な場合があります。
- (※3)担保:土地・建物※不動産に根抵当権を設定させていただきます。
- 実質年率は15%以下。実質年率とは、(金利+諸費用)の合計を年率で計算した利率。
- 利息制限法の利率(15%)を超えることは無い。
- 返済期間は最大の年数であり、審査結果により短縮される。
- 保証人は、「法人代表者」や「担保提供者」に求められることがある。
- 金融庁財務局「貸金業者登録一覧」、日本貸金業協会「協会員名簿」、各都道府県の登録(例:東京都)を閲覧し、適法な業者のみをリストアップしている
こちらを参考に、ご自身に合う不動産担保ローンを探してみてください。
ARMS会計株式会社では事業やライフプランに合わせた資金プランニングを支援しています
不動産担保ローンは、正しく利用すれば大きな助けになりますが、判断を誤ると生活や事業に深刻な影響を与えかねません。
ARMS会計株式会社では、公認会計士・税理士としての経験を活かし、借入目的や返済計画をお客様の事業やライフプランに合わせて設計しています。
資金調達に関するご相談は、ARMS会計株式会社/太田昌明税理士事務所までお問い合わせください。
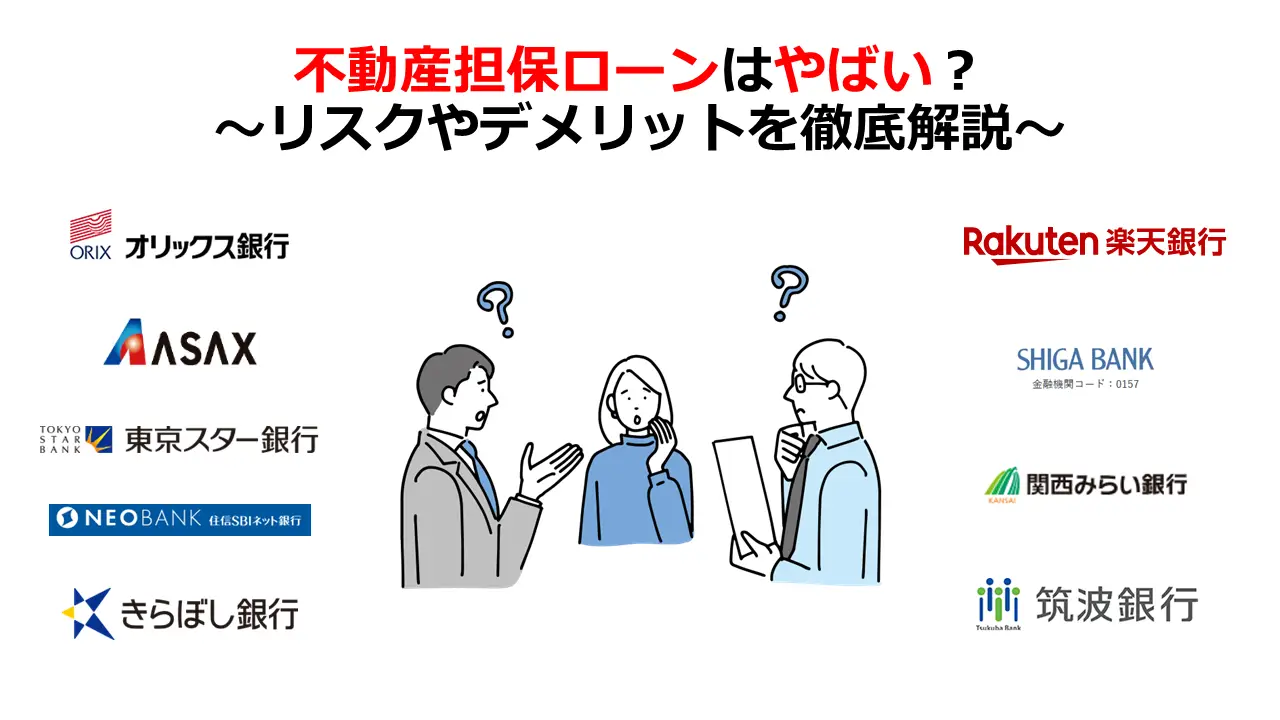





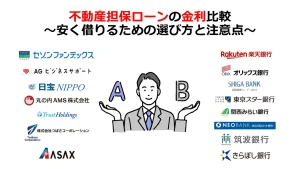


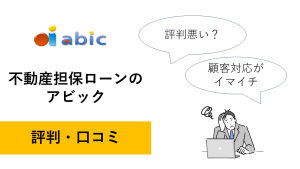
コメント