つばさコーポレーションで審査落ちする理由
- 融資金額に対して担保評価が不足している(不動産価値・担保順位)
- 信用情報の問題(延滞・債務整理・金融事故によるブラック扱い)
- 資金使途や返済計画が不明確である
- 申込内容や必要書類の不備
- 収入や既存借入の状況から返済能力が不足している
つばさコーポレーションで審査落ちした場合にやるべき対応策
不動産担保ローンは「不動産さえあれば誰でも借りられる」と思われがちですが、実際には担保価値だけでなく、申込者の信用情報や返済計画まで厳しくチェックされます。
つばさコーポレーションの不動産担保ローンも例外ではなく、準備不足のまま申し込んでしまうと「審査落ち」の結果に直面することがあります。
では、なぜ審査に落ちるのか。そして、落ちてしまった後にどう行動すべきなのか。
私は公認会計士・税理士として、中小企業オーナーや個人事業主の資金調達に数多く関わってきました。
その中で「否決から可決に変わった事例」や「不動産担保に頼らず資金を繋いだ方法」を実際に見てきています。
融資の審査基準は公開されませんが、実務の現場には一定の傾向があるのです。
本記事では、つばさコーポレーションの不動産担保ローンで審査落ちする典型的な理由と、審査を突破するための具体的な準備、そして落ちた後に取るべき対応策を、専門家の立場から整理しました。
1988年生まれ
公認会計士・税理士
2014年 EY新日本有限責任監査法人 入所
2021年 ニューラルグループ株式会社 入社
2022年 株式会社フォーカスチャネル取締役 就任
2024年 太田昌明公認会計士・税理士事務所 開業
2024年 ARMS会計株式会社 代表取締役社長
2025年 東京税理士会向島支部 幹事(役員)【税務支援対策部】
前職では上場会社の経理財務部長として勤務し、現在は経理・財務支援サービス会社を経営しています。
財務担当として銀行取引経験があり、メガバンク・地方銀行・日本政策金融公庫などの対応をしていました。これまでに取り扱った融資規模は、1件あたり1,000万円~10億円です。
また、不動産業界の会計監査に携わっていたので不動産業界の知見(減損会計による不動産の収益性の計算・判定・時価評価、SPCのスキーム・ローン検討等)や、不動産賃貸業(賃貸事業所・オフィス・クリニック向け)の経営のサポート(主に経理・税務申告対応)経験を活かし、不動産担保投資・不動産担保ローン全般の相談も受けております。
つばさコーポレーションの不動産担保ローンの審査に落ちた理由5選
不動産担保ローンは「不動産があれば誰でも借りられる」と思われがちですが、実際には審査基準をクリアしなければ融資は実行されません。
つばさコーポレーションでも同様で、担保価値や信用情報だけでなく、返済計画や書類の整備状況まで含めて多角的に判断されます。
以下、公認会計士・税理士として中小企業の資金調達支援に数多く携わってきた私の経験を踏まえ、審査に落ちる典型的な5つの理由を解説します。
融資金額に対して担保評価が不足している(不動産価値・担保順位)
不動産担保ローンの最大の審査ポイントは「担保価値」です。
例えば、1億円の融資希望に対して、不動産の評価が6,000万円しかなければ、審査通過は難しくなります。
さらに、既に他の金融機関が第一順位で抵当権を設定している場合、担保順位の劣後も審査落ちの要因です。
実務では「時価よりも低めに見積もられる」ことが多く、固定資産税評価額や路線価といった公的基準よりもさらに厳しめの査定がなされます。
私がサポートした案件でも「自社の試算では十分」と考えていたオーナーが、金融機関査定では2割以上低く評価され、結果的に希望額の半分しか借りられなかったことがありました。
信用情報の問題(延滞・債務整理・金融事故によるブラック扱い)
延滞や債務整理の履歴が信用情報機関に登録されている場合、つばさコーポレーションを含め多くの金融機関はリスクを避けます。
特に、カードローンやクレジットの延滞は見落とされがちですが、融資判断に直結します。
私が相談を受けた事例でも、法人代表者が過去に個人のカードローンを延滞していたため、法人としては黒字決算にもかかわらず審査落ちした事例がありました。
「会社は健全でも代表者個人の信用で否決される」点は、中小企業経営者にとって盲点となりやすいです。
資金使途や返済計画が不明確である
「運転資金に充てる」「借入の一本化」といった大まかな説明では、金融機関を納得させられません。資金使途が具体的に示され、返済計画が現実的であることが不可欠です。
例えば「新規事業のため」と申請しても、事業計画書が粗雑で数字の裏付けがなければ信頼は得られません。
私は支援先に対し、試算表やキャッシュフロー計画を整備してから申請するよう強く助言していますが、この準備不足が原因で落ちるケースは非常に多いと感じます。
申込内容や必要書類の不備
単純な記載ミスや書類不足でも、審査落ちの原因となります。
特に法人の場合は、直近数期分の決算書や納税証明書の提出が必須ですが、これを揃えていない申請者が意外に多いのです。
私が相談を受けた案件でも、提出した決算書が税務申告の内容と一部食い違っていたため、確認作業に時間がかかり、その間に審査が否決された事例がありました。
金融機関は「準備が整っていない=管理体制が不十分」と捉えるため、誠実かつ正確な提出が求められます。
収入や既存借入の状況から返済能力が不足している
担保があっても、返済原資が不明確であれば融資は認められません。
金融機関は「担保を売却すれば回収できる」だけでなく「安定した返済が継続できるか」を重視します。
特に事業者ローンでは、赤字続きや資金繰りが逼迫している場合、審査は厳しくなります。
私の経験では、黒字決算でも「売上の季節変動が大きい」企業は返済能力の不安定さを理由に否決されたケースがありました。
つまり、担保と同じくらい「事業の継続性」や「返済の見通し」が重要なのです。
審査に通過するための具体的な準備と対策
審査落ちの多くは「事前準備の不足」が原因です。
不動産担保ローンは担保だけでなく、申込者の返済能力や計画性を重視します。
裏を返せば、必要な準備を整えれば通過できる可能性は大きく高まります。
以下、公認会計士・税理士として企業や個人の資金調達をサポートしてきた経験から、特に効果的な4つの準備ポイントを解説します。
返済能力を示す収支計画と証憑を整える
金融機関が最も気にするのは「貸したお金がきちんと返ってくるか」です。
そこで重要になるのが、現実的な収支計画とそれを裏付ける証憑です。
例えば、法人なら「試算表・資金繰り表・受注契約書など」を組み合わせて「返済原資がある」ことを具体的に示す必要があります。
個人事業主や個人であれば、確定申告書や給与明細を揃えて「安定した収入がある」ことを証明することが有効です。
私の関与先でも、単に「黒字決算です」と伝えるだけでは不十分で、翌期の資金繰り計画を数値で示したことで審査通過に繋がった事例があります。
担保評価を高める工夫をする
担保不動産の評価額は、融資可否に直結します。
評価が低いと判断されれば、十分な担保を持っていても希望額に届かないことがあります。
ここで有効なのが「共同担保の提供」や「第三者の保証協力」です。
また、不動産鑑定士による評価書を取得して金融機関に提示することで、客観的な裏付けを示すことも有効です。
実務では、同じ物件でも金融機関ごとに評価額が異なることが少なくありません。
私の経験では、自行査定では5,000万円と評価された物件が、鑑定評価を添付したことで6,500万円に見直され、融資枠が広がったケースもありました。
信用情報を事前に確認し改善に努める
延滞や債務整理などの情報は信用情報機関に登録され、審査で必ず確認されます。
申込前に自分の情報を取り寄せ、問題があれば対応策を考えることが大切です。
もし過去に延滞があっても、完済後5年程度で情報は消えます。
短期的には難しくても、中長期で融資を目指すなら「まずは延滞の解消」「少額でも確実な返済を続ける」など、改善の姿勢を示すことが重要です。
「少額の延滞を整理してから再申込したことで、以前は落ちた融資に通った」という事例もあり、信用情報の整備は侮れない審査対策です。
専門家に相談して申込条件を調整する
自己判断で申込を進めると、条件が合わずに審査落ちしてしまうことがあります。
会計士や税理士など専門家に相談することで、金融機関に響く申込内容に調整できる可能性があります。
例えば、「借入金額を少し下げて分割実行にする」「担保の組み合わせを変える」といった提案は、経験豊富な専門家だからこそアドバイスできる部分です。
知り合いの税理士から聞いたケースですが、金融機関との交渉に立ち会った際、申込者が希望する条件のままでは否決だった案件を、返済期間を延長したり、金利調整する条件変更で可決に持ち込んだという事例があります。
こうした微調整は、申込者本人だけでは気づきにくいポイントです。
つばさコーポレーションの不動産担保ローン審査落ち後の対応策3選
審査に落ちてしまったからといって、すぐに資金調達を諦める必要はありません。
不動産担保ローンには他の金融機関もあり、事業者向けには担保を使わない資金調達手段も存在します。
また、個人であれば、条件を絞れば利用できるローンもあります。
以下、公認会計士・税理士として多くの相談を受けてきた経験から、審査落ちの後に検討すべき具体的な3つの対応策を紹介します。
他社の不動産担保ローンに再申込する
つばさコーポレーションで否決されても、他社では条件が合致して融資が通ることは珍しくありません。
なぜなら、不動産の評価方法や重視する審査基準は金融機関によって異なるからです。
例えば、私のある支援先では、A社では担保評価が低すぎて融資不可となったものの、B社では別の評価手法を用いた結果、同じ物件が高く評価され、希望額に近い融資が実行されました。
ポイントは「同じ条件で再申込するのではなく、担保物件や借入額、返済期間などを調整して臨む」ことです。
この点、専門家に相談しながら条件を整えれば、審査通過率を高められます。
法人・個人事業主はファクタリングを活用する
事業者であれば、不動産を担保にせずとも資金を調達できる方法があります。
それが「ファクタリング」です。
売掛金を譲渡して資金化するため、信用情報に不安があっても利用できる場合があります。
実際に、私の支援先の中には「銀行融資は断られたが、ファクタリングで運転資金を確保し、その後の業績回復で再び融資に通った」ケースもありました。
ファクタリングは手数料がかかるため万能ではありませんが、一時的な資金ショートを防ぐ緊急回避策として有効です。
個人は消費者金融や銀行カードローンを検討する
個人で事業資金や生活資金を必要とする場合、不動産担保ローン以外のローンに目を向けるのも選択肢です。
消費者金融は少額・短期の利用に適しており、銀行カードローンは比較的低金利で利用できるケースがあります。
注意点は「借入額を小さく抑えること」と「返済計画を明確にすること」です。
私が相談を受けた中には、担保ローンに落ちた後、銀行カードローンを活用して一時的に資金を繋ぎ、その後に不動産売却で一括返済した方もいました。
消費者金融やカードローンは相対的に審査が甘く利便性が高い一方で、金利負担が大きいため、短期的な資金繋ぎに限定して使うのが賢明です。
【比較表】つばさコーポレーションに代わる不動産担保ローン
| セゾンファンデックス | AGビジネスサポート | 丸の内AMS | ファンドワン | トラストホールディングス | 日宝 | MIRAIアセットファイナンス | MRF | つばさコーポレーション | 総合マネージメントサービス | マテリアライズ | アサックス | JFC | アビック | デイリーキャッシング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | |||||||||||||||
| 総合評価 | ( 9.7点 ) | ( 9.6点 ) | ( 8.1点 ) | ( 7.8点 ) | ( 7.7点 ) | ( 7.1点 ) | ( 7.0点 ) | ( 6.7点 ) | ( 6.3点 ) | ( 6.1点 ) | ( 6.0点 ) | ( 6.0点 ) | ( 6.0点 ) | ( 6.0点 ) | ( 5.4点 ) |
| 金利 | 3.15~9.9% | 公式サイト参照 | 3.8~15% | 2.5~18% | 3.45~7.45% | 4~9.9% | 4~9.5% | 4~15% | 4~15% | 3.4~9.8% | 4.8~9.8% | ~7.8% | 5.86~15% | 2.98~15% | 5.2~13% |
| 融資速度 | 最短3日 | 最短3日 | 最短2日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短翌日 | 最短数日 | 最短即日 | 最短3日 | 最短翌日 | 最短3日 | 3日~1週間 | 最短2日 | 非公開 |
| 借入限度 | ~5億円 | 100万円~5億円 | ~5億円 | ~1億円 | ~10億円 | ~5億円 | ~5億円 | ~3億円 | 非公開 | ~5億円 | ~3億円 | ~10億円 | ~5億円 | ~50億円 | ~8,000万円 |
| 返済期間 | 5~25年 | ~30年(※1) | ~35年 | ~35年 | ~30年 | ~30年 | ~20年 | ~3年 | ~30年 | ~35年 | ~20年 | ~30年 | ~10年 | ~30年 | ~30年 |
| 保証人(※2) | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 可能性有 | 原則不要 |
| 抵当順位 | 不問 | ※3 | 不問 | 非公開 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 原則1位 | 不問 | 非公開 |
| 評判を見る | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ | 評判・口コミ |
| 公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
※注釈
- (※1)元利均等返済:最長30年(360回以内)、元金一括返済:最長30年(360回以内)
- (※2)法人契約の場合は原則代表者の連帯保証が必要。担保提供者の連帯保証が必要な場合があります。
- (※3)担保:土地・建物※不動産に根抵当権を設定させていただきます。
- 実質年率は15%以下。実質年率とは、(金利+諸費用)の合計を年率で計算した利率。
- 利息制限法の利率(15%)を超えることは無い。
- 返済期間は最大の年数であり、審査結果により短縮される。
- 保証人は、「法人代表者」や「担保提供者」に求められることがある。
- 金融庁財務局「貸金業者登録一覧」、日本貸金業協会「協会員名簿」、各都道府県の登録(例:東京都)を閲覧し、適法な業者のみをリストアップしている
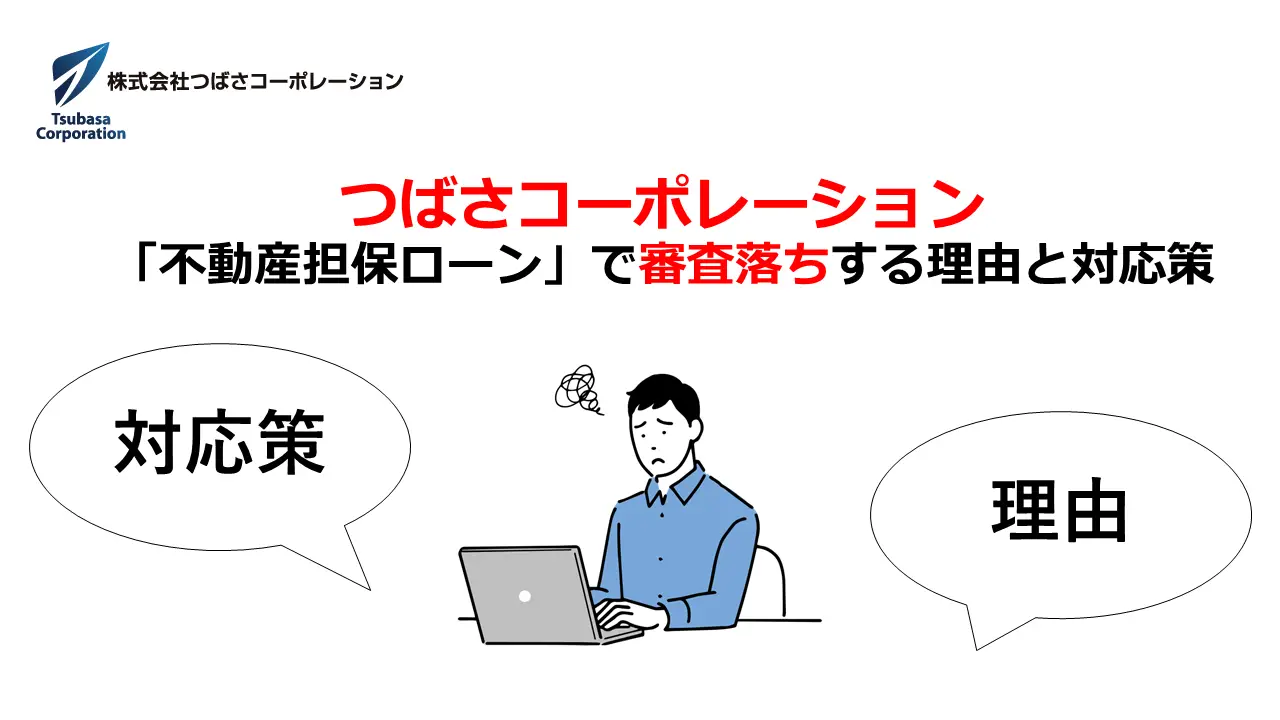






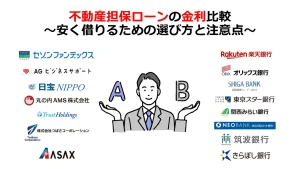


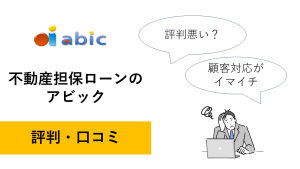
コメント